投資家が「お金」よりも大切にしていること(藤野英人著)を読んだ。
私は経理事務の仕事をしていた経験があるにもかかわらず、お金のことが苦手。
もちろん仕事では1円の狂いもなく執念で計算していましたが、プライベートではお小遣い帳や家計簿をつけていない。
やってみたこともあったけれど、必要なものを買っているのに「うわー、今日はこんなに使ってしまった!」などと思ってしまい、自分がケチ臭くなっていくような気がして、イヤになってやめてしまった。
今回、この本を読んだきっかけ。
- 「お金」についての知識をあらためることが、自分には必要な気がした
- 投資家という目線からの「お金」はなんなのかに興味があった
読んでみたら、この本は「お金」についてのことというよりも、むしろ生きていくうえでの考え方、生き方について語られていた。
いや~、勉強になった!
以下、ネタバレ注意ですが、「投資家が「お金」よりも大切にしていること」の紹介!
スポンサーリンク
「経済」の語源とは?
「経済(エコノミクス)」の語源、ご存じでしょうか?
私は「経済」というと、「お金の流れ」というような、「お金」絡みの印象を持っていた。
ところが、なんと「経済」の語源は、「共同体のあり方」!
著書の中で、佐藤雅彦氏と竹中平蔵氏の共著「経済ってそういうことだったのか会議」から引用されている。
「佐藤さん、エコノミクスって、ギリシャ語の”オイコノミコス[oikonomikσs]”から来ているんです。オイコノミコスとはどういう意味かといいますと、共同体のあり方、という意味なんです」
そして藤野さんは、書いている。
経済というものは、その語源からして「みんなの幸せ」を考えるものなんですね。
藤野さんの座右の銘は「自他不二(じたふじ)」という、もともとは大乗仏教の考え方とのこと。
意味は、以下。
自分の喜びは他人の喜びにつながり、他人の幸福は自分の幸福につながる。だから、みんなの幸せを考えることが、最終的に自分の幸せを考えることにつながっていく――
ところが今の日本の現状は、「自分さえ良ければいい」という人が多すぎると、警鐘を鳴らす。
すべての人が幸せになるのはむずかしいかもしれないが、むずかしいから諦めるのではなく、理想を目指すべきなのだと。
経済とは、お金を通してみんなの幸せを考えること――このことを、ぜひみなさんは覚えていてください。
↓「自分さえ良ければいい」のは違うという記事、私も書いてます♪
「孤独」を埋める消費はステキではない?
藤野さんは、「人は、ただ生きているだけで価値がある」と書いている。
例えば、生産活動ができない赤ちゃんであっても、赤ちゃんがいることでベビーグッズの需要があるというように。
そして、「もっともステキじゃない」お金の使い方として、孤独を埋めるために消費すること、を上げている。
例えば、衝動買い。
例えば、シニア層の投資信託。
孤独を埋めるサービスや商品が売れて、孤独を煽ることで、孤独な人がさらに増えていくと。
確かに「寂しさ」「孤独」につけこんで、良き理解者のような雰囲気で近づいてきて商売に結び付けるのは「ステキではない」ように思う。
だけど、うーん、これは、ちょっとした解釈の違いだけど、「寂しさ」に寄り添う、「寂しさ」を和らげるサービスは「ステキではない」とは、私は思わない。
だって、人間、基本、一人だと思い「孤独だな」と感じてしまうことってある。
所詮、人間は一人なんだから「孤独に耐えろ」ではなくて、「孤独を和らげること」必要じゃないですか?
「ああ、自分は一人じゃないなあ」と感じる瞬間に救われることないですか?
べったり「依存」は良くないにしても。
「孤独」を埋めるために、理性を失って消費してしまうことや、「孤独」につけこんで味方面して金儲けする商売はステキじゃないですが、「孤独を和らげる」ようなサービスは、逆にステキなのではないかなあ……。
「会社」のもともとの意味は「仲間」
英語で会社はcompany(カンパニー)、そして、この言葉のもともとの意味は「仲間」です。
中略
株式は英語でshare(シェア)です。「食べ物をシェアする」とか「シェアハウス」のシェアですね。「分配」であり、「分け与えること」です。
藤野さんは、興味深い話を紹介している。
太古の昔、人間はアフリカで細々と生きていた弱い哺乳類だった。
災害が起こり、人間の祖先も絶滅の淵に立たされた。
生き残った人間のうち、さらに生き延びることができたのは、血縁関係でなくてもお互いに助け合い、少ない食べ物を分かちあったグループだけだった。
つまり、生き延びるためには、「協力」しあい、「シェア」する精神を持つことが必要。
そして、もうひとつ。「谷底の神父」という寓話を紹介している。
谷底の教会に、信仰深い神父がいた。ある時、大洪水が起きた。
村人が教会に来て「神父さん逃げましょう!」と言ったが、「大丈夫、神様を信じているので奇蹟が起こる」と言って逃げなかった。
どんどん洪水の水が増えてきて、村人がボートで教会に来て「神父さん逃げましょう!」と言ったが、「大丈夫、神様が助けてくださる」と屋根に上って祈りを続けた。
水が屋根まで迫ってきて、村人がヘリコプターで助けに来た。「神父さん逃げましょう!」と言ったが、「大丈夫、必ず神様が助けてくださる」と言って逃げなかった。
結局、神父は死んでしまう。天国に行き、神父は神様に「なぜ、助けてくれなかったのですか」と聞く。
返ってきた答えは「3回も助けをやったぞ」
これはつまり、「奇蹟は人が起こすもの」だということ。
社会=ひとりの人間
本を読んで、「うわぁ、その考え方か!」と、気付かされたことがある。
藤野さんは「会社とは、多様な人間の集合体」であり、ポジティブ、ネガティブ、がんばり、怠けなどが集まっている「ひとりの人間」のようなもの、と書いている。
ひとりの人間の中にも、ポジティブ、ネガティブ、がんばり、怠けなどがあるから。
藤野さんは「会社」を「ひとりの人間」のようなものと書いていますが、私はちょっと考え方を変えて「自分と関わる社会」=「ひとりの人間」=「自分」なのではないかと気付いた。
だから、自分にも良い面と悪い面があるように、周りの状況にも良い面と悪い面があっても当たり前で、誰かのことを見て「ああいう人、嫌いだなあ」と思う人は、実は自分の中にある、自分が嫌いな部分なのではないかって。
「ああいう人にはなりたくないなあ」と思う人は、「ああいう人になってしまうこともできるけど、その選択はしたくない」という自分の決意なのではないかって。
つまり、どういうことかというと、
自分の周囲の状況は、自分の一部(あの人もこの人も!)であり、自分が作っている、
状況を変えたいのであれば、自分が変わること(どうバランスをとるか)が必要。
※むむ、このテーマ、じっくり考えたいほど深い。ぼそっ。
「運」と「思い切り」
”投資は、「お金」ではなく「エネルギー」のやりとり”
と藤野さんは書いている。
駅のトイレの清掃員女性の話。
女性は「早くきれいに磨ける方法をいつも考えている」「汚れているところは、ファイトがわく」と言う。
自分の仕事にエネルギーを注ぎ、給料だけではなく、世の中からいろいろなお返しをもらっている、彼女こそ、偉大な投資家だと思ったのだそうだ。
投資とは、いまこの瞬間にエネルギーを投入して、未来からのお返しをいただくこと
ただ、うまくいくかどうかは「運」次第であり、「思い切り」が必要だと。
今のエネルギー投資が未来を変える
上で引用している通り、本を読んで、
「(お金だけではなく)今、エネルギーを注ぐことで、未来からお返しを頂く(=投資)」
ということを受け取った。
ただ、エネルギーを注いでも、必ずうまくいくとは限らず、運に左右される。思い切って、やることが必要。
ワタクシ的にもうひとつ付け加えるなら、エネルギーを注いだことが必ずしもうまくいくとは限らない。
一生懸命やればうまくいくなんて幻想だ。
しかし、だからといって、一生懸命やることは無意味ではない。
なにかに全力で挑戦する、
例え結果が出せなかったとしても、
そのことを通して培ったパワーは、人生を生き抜く底力になる!
いやはや、お金のことというより、生きる姿勢を教えられたような、再確認させられたような本。
お金については、また勉強が必要……、
というより、実は、生きる姿勢を学ぶ=お金の勉強、なのかも?
※追記:その他、印象的だったこと 備忘録
その1、スタートトゥデイ(ZOZOTOWN運営)の社是は「カッコいいこと」
・・・へぇー。これ、いいですね! 「ルールだから、ダメだよ」と言われるより、「カッコ悪いから、やめとけば?」と言われる方が、抑止力ある。
その2、「失われた20年」と、”受動態”で語られていることに納得がいかない。
・・・うーん、被害者になっているというより、言葉の響きで語られてるのかしらね? 受け身になってしまうところ、確かに日本人的。
あなたの”一生懸命”を応援します☆
複数ブログ運営中!更新報告はtwitterから!フォローお願いします!
Follow @Ruca_moon
スポンサーリンク

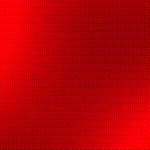


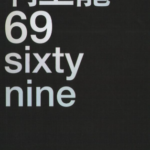


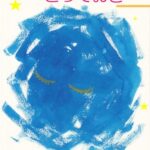







コメントを残す